公益社団法人八戸青年会議所創立60周年記念対談
Talking about Hachinohe vol.2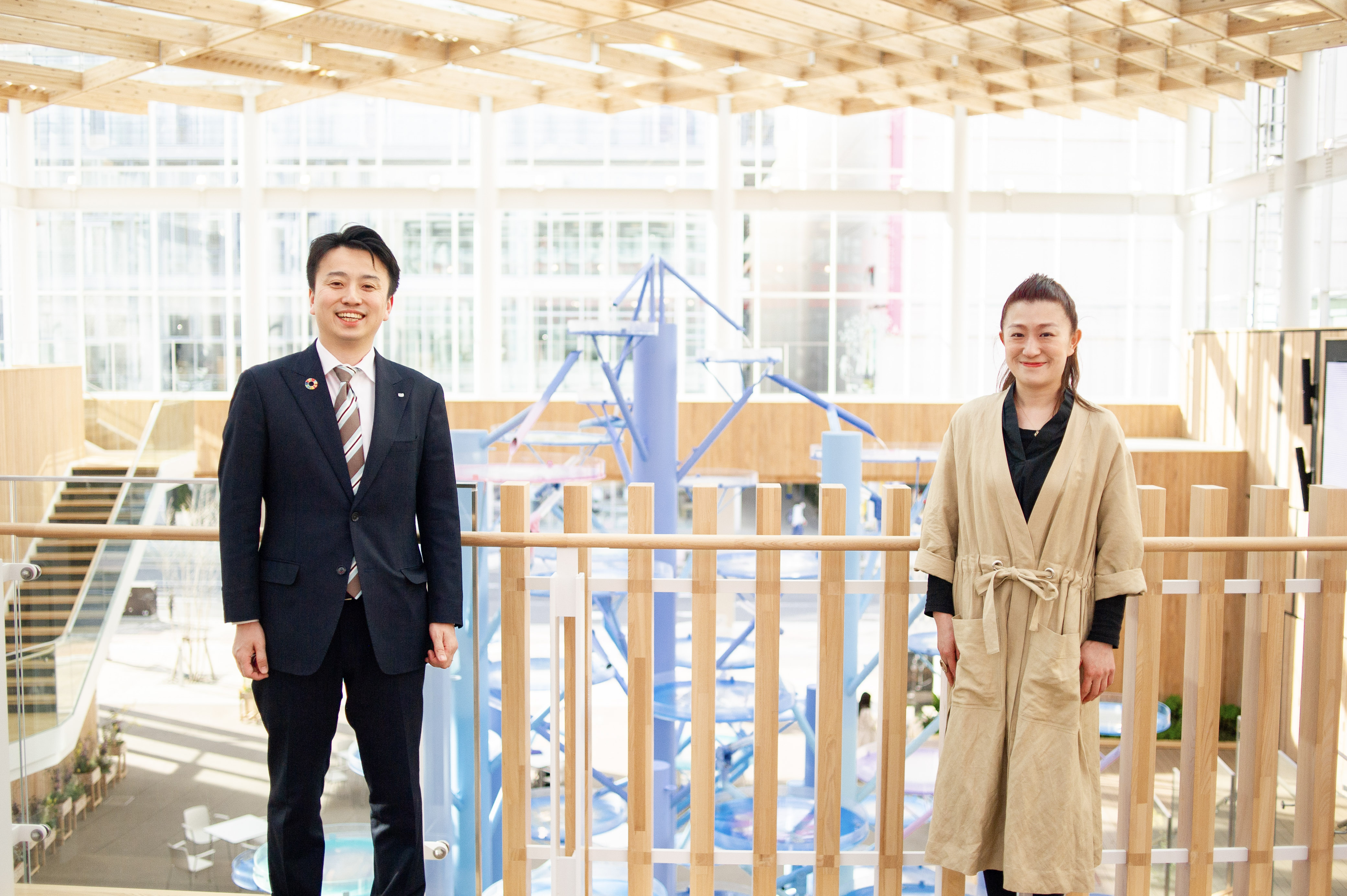
八戸三社大祭やえんぶり、古くから私たちは郷土愛の拠り所として、伝統的な文化や芸能に暮らしを重ねてきた。時に、歌い、舞い、心の内に秘めたエネルギーを爆発させるかのごとく、自らを表現することで郷土を想い、愛し続けてきた。私たちの郷土愛の深淵を探り当てるもの―。その一つがアートだ。今回は八戸の暮らしぶりをアートと照らし合わせてまちづくりに取り組んでいる今川和佳子氏との対談を通して、八戸の魅力を探る。
「都会暮らしで気付いた八戸の魅力」
金入健雄理事長(以下、金入):今川さんは様々な地域でアートを通じた活動をされているかと思いますが、なぜ、今のお仕事やアートプロジェクトに関るようになったか、その経緯をお聞かせいただけますか?
今川和佳子(以下、今川):油絵の絵描きをしている父の影響もあって、高校の時に美大進学を希望したのですが、「芸術でやっていけるわけがないだろ!」と父に一喝されあっさり諦めました(笑)。それで、小学校からバスケットボールをやっていたこともあって、運動生理学を専攻して東京の大学に通っていました。でも、ずっと芸術には興味があり、また東京の下北沢に住んでいたこともあって、音楽や芝居を見に行ったり、ボランティアでアートイベントに関わったりしていました。家族のことがきっかけで2007年に八戸に帰ってきたんですが、その時にちょうど「はっち」を応援する市民グループの活動が八戸で盛んになっていてそれに参加していたんです。そうしている間に、2008年に本格的にはっちを立ち上げる準備室ができて、私も市の嘱託職員コーディネーターとして採用されました。それまでは東京で大学に通って、仕事をしていくというのが自分の価値観の中にはあったんですが、東京で暮らしているうちに、八戸の良さが見えてくるようになりました。そのタイミングではっちの動きが加速化してきて、すごく可能性があるなと思い、ここで何か活動ができるのだったら楽しく暮らせるんだろうなって思えたんです。
金入:子どものときにお父様が画家という影響もありながらはっちへの関わりが今の活動につながる一つのきっかけだったんですね。はっちのコンセプトの一つにまちを大切に思う。という考え方があります。行政が先導したモノなのに、用途が限定されすぎず地域を大切にしながらも自由に市民が参加できるプロジェクトや空間が広がる舞台のようなコンセプトが作られ、今や多くの市民に受け入れられているわけですが、当初はかなり画期的だったんじゃないかと思うんですよね。そういう市民目線で地域のことをプレゼンテーションするようなしかも自由度があるコンセプトに対して当時はどのように思っていたのでしょうか?
今川:地域の課題にアートの視点から取り組むアートプロジェクトは、どちらかというと、アーティストが主役であることが多かったように思います。でも、はっちはその逆で、主役は市民であることを大切にしていました。その過程で、アーティストや私たちスタッフが、いかに市民を輝かせられるか?当時の館長の風張さんや、ディレクターの吉川さんにはそうした思想の大切さを教え込まれました。


「八戸レビュウから見えた八戸人の精神」
金入:最初のプロジェクトは「八戸レビュウ」だったかと思います。梅佳代さん、浅田政志さん、津藤秀雄さんが写真家として来て、市民の写真を撮って、市民が文章を書くプロジェクトでしたよね。そのコンセプトがまさに地域の人が主役というところが全面に押し出された企画だったように思います。今川さんは「八戸レビュウ」とはどのような関わりがあったのですか?
今川:写真家と被写体となる市民のマッチングや、撮影場所の設定や段取り、撮影の同行などを担当していました。
金入:「八戸レビュウ」のプロジェクトでそのアーティストとの関わりがあったと思いますが、市民の皆さんの反応はどうでしたか?
今川:思っていた以上に積極的でしたね。それは3人の写真家の人柄とかコミュニケーション力によるところが大きいと思います。また当時同じく事業を担当していたコーディネーターの渡邉君が、かなり細やかに動いてみんなを繋いでいましたね。
金入:なるほど。色々な写真がありましたね。鳥の格好をしたり、公園で煎餅を焼いたり…。
今川:ですね。そういうことを「やろうやろう!」みたいなノリでみなさん協力してくれました。もしかしたら、それが八戸の人の精神なのかなと思いました。撮影にあたって、こちらはもっと身構えていたんですけれど、市民の皆さんはすごく自然に受け入れてくれるんです。この気質って何だろうなって。もしかしたら、お祭りとかが身近なところにあるのが大きいのかなとは思っています。こちらが撮影する皆さんを盛り上げるっていうよりは、むしろ私たちが鼓舞されて撮影が進んでいったんですね。発見の連続でした。撮影に行くたびに会う人みんな素晴らしくって、八戸にはこんなに多様な人がいるんだって思いました。
金入:港町だからなのか独立心を持っている人が多いというか、自らの価値観にもとづいて大胆に行動していくような気質があると感じます。八戸三社大祭もそうですが、同じような精神性を感じる八戸発祥と言われるデコトラにも、「これが俺たちには必要なんだ!」という精神があるのかなと。海から拓けたまちということで、新しい物事を受け入れる気質だったり、変化の中で新しい物事にチャレンジするという感性があるのかなと。

「デコトラ文化の発祥は八戸」
今川:そうですよね。私も、デコトラの取材では金入さんとご一緒させていただきましたね。生みの親と呼ばれる夏坂照夫さんのインタビューです。私たちが行ったのは「デコトラヨイサー!」というプロジェクトでした。ベトナム在住でオーストラリア人のスーさんという女性アーティストが、デコトラの発祥の地が八戸であることを突き止めました。そこで、ベトナムのビーズや日本の着物などを使って、裁縫が得意な女性たち等といっしょにデコトラを制作するという企画を考えました。
金入:布でデコトラを作ってその中に入って踊るというプロジェクトでしたかね?
今川:そうですね。獅子舞や、虎舞みたいな。ボディーがデコトラになって3人入って踊るものでした。
金入:すごい発想ですよね。はっちがデコトラをテーマに掲げた時は本当に驚きました。行政が関わる中で、トラックを個性豊かに改造するというのはなかなか手が出しづらい企画だったと思うのですが、結果的に今川さんが関わったデコトラヨイサーのプロジェクトは、全国からデコトラが集まって競い合う八戸デコトラ祭りにも派生しましたよね。こうしたプロジェクトを八戸市がしっかり先導して、これだけ不寛容な世の中になってきている中で、独自性というか土着性というか、本質的な部分を見据えて、突き抜けたプロジェクトとして成長していったと思っていて、それがすごいなと思いました。今川さんと一緒に夏坂さんにインタビューさせてもらって凄く印象的だったのが、当時八戸から築地にトラックが行くときに、八戸の魚は新鮮だという事と、自分たちのプライドで築地の手前でトラックを降りて、ピカピカに磨いてから築地に入る。
今川:そうそう服も着替えてね(笑)。
金入:それを見て築地の人たちは道を空けてくれたという。そういう港町の誇りを表現するものがデコトラであり、それがエスカレートし、全国のトラックの運転手同士で広がっていった。それが、八戸発祥というのがカッコいいなと思います。
今川:それまでデコトラは、違法なもの、反社会的なもの、というネガティブな印象を持たれることがあったと思いますが、実はその美意識や精神性みたいなものに惹かれる人も多いということも分かりました。スーさんは、デコトラのイメージをポジティブなものに変え、その文化に気付かせる大事な存在だったんです。時にこのように、外からやってくるアーティストの新鮮な目線や感性によって、地域にとっては当たり前だと思っていることが花開くことがあります。それがアーティストのすごいところ。そして夏坂さんをはじめ、トラック野郎のみなさんの心意気には心底惚れるものがありました。それは、家族愛や郷土愛といったものです。車体に「八戸」という地名を書き付けることで、郷土愛や、郷土を背負って立つ心意気を強烈に表していると思います。家族と離れている時間も長いので、奥さんや子どもの名前を車体に書いたり、車の名前にしたりすると聞きました。そして家と同じようにくつろげるように、車内を自分好みに装飾したり。その飾り1つ1つを、昔は手作りしていたそうです。そうした感性に、スーさんは八戸ならではのものを感じたと言います。三社大祭の山車にそっくりだよね、という話もでました。確かにあのデコっている感じは、そっくりですね。
金入:スーさんの視点を借りることで、デコトラが1つの文化として捉え直されたとも思います。それは、八戸の本質だったり、魅力の発信だったりに繋がると思います。そういう意味でアーティストと地域の関りが素晴らしく発揮された例として感じられますね。
「複雑な文化が絡み合っている魅力」
今川:「酔っ払いに愛を~横丁オンリーユーシアター~」は10年やっていますが、これは空き店舗の複数個所を劇場にして、ダンスや芝居などをハシゴして見て歩くという企画。それ以前から、横丁は観光資源として注目されていましたが、「お酒を飲む」という切り口以外の取り組みとして、アートプロジェクトは面白いね、ということで始まりました。はっち開館前の2009年のことでした。このプロジェクトの特徴は、はっちやアートに関わる専門家だけで作るのではなくて、横丁周辺の中心商店街の方々もメンバーになり、実行委員会形式で進めたこと。アートをやることだけが目的ではなくて、「街といっしょに作りあげるプロジェクト」というミッションを持ったものでした。そしてそこにダンサーなどのアーティストが入り込み、横丁という街の魅力をいっしょに探し出していく。今では横丁のお店の方々に「今年は誰が出るの?」と話題に出してもらえるほど、横丁に浸透しつつあるし、協力していただいています。
金入:アートがまちの潤滑油になっているということですね。
今川:それによってお店の売り上げが上がるわけではないけれど、やり続けることで、まちに話題を生みコミュニケーションが活性化します。
金入:地域の魅力や、地域の特性に外からの視点を組み合わせて様々なプロジェクトを立ち上げているんですね。私たちが昨年行った「朝活スタイル」という事業でも朝型のライフスタイルに焦点を当て朝市や種差海岸での早朝ヨガなどを通してこのまちの魅力を発信してきました。これもまた港町だからこそ生まれてきた元来の八戸が持ついわば日常に、私たち自身が価値を見出し発信するという意味があったと考えています。本年もこのような新たな八戸のスタンダードと言えるような、まちの魅力を発信していければと考えています。それでは、今後やりたい事と考えていることを教えてください。
今川:アーティストが滞在制作できるような、レジデンス施設を作りたいですね。これまで多くのレジデンス事業に関わってきましたが、いろんな視点が生まれたり、参加した市民とアーティストが仲良くなったり、よい循環がたくさん生まれるのを目撃してきました。八戸を好きになってもらって、事業が終了しても何度も足を運んでもらえるように、その受け皿となるアーティスト専用の場所が作れたら、と思っています。
金入:アーティスト達に八戸に来てもらうような環境を作って、このまちのどんな魅力とアーティストが出会ってほしいと考えていますか?
今川:八戸は、例えば青森で言うところの「ねぶた」のように、誰もがピンとくるものというよりは、一言で表しきれない、ある種の分かりにくさがあると思います。そういう複雑な文化が絡み合っているところが魅力かなと。なんでもありのテンコ盛りのような状態も、アーティストには独特に映るようですね。そういった一つ一つに光をあて、市民と外からやってくるアーティストとで紐解いていくことで、人口減少や少子高齢化が押し寄せるこれからの時代にも、地域の中にエネルギーを湧き起こしていけるのではないかと考えています。
 八戸まちなか広場 マチニワ シンボルオブジェ「水の樹」前にて
八戸まちなか広場 マチニワ シンボルオブジェ「水の樹」前にて
八戸青年会議所とは
八戸市近郊に在住する20歳から40歳までの青年経済人の集まりで「奉仕」「修練」「友情」を活動の基本として「明るい豊かな社会の実現」を目指し、八戸のまちに住み暮らす人々や子どもたちの笑顔のために活動を続けている団体。今年で創立60周年を迎え、現在で約130名の現役会員を擁する。
今川和佳子(いまがわわかこ)
青森県八戸市出身。東京在住時代に、食やファッションの企画、営業に関わる。2007年八戸に戻り、6年間コーディネーターとして八戸ポータルミュージアムはっちの立ち上げに関わる。地域の歴史や文化を、アーティストや市民とともに再発見、発信するアーティスト・イン・レジデンス事業を主に担当、街歩きのプロジェクトや食を絡めた事業にも関わる。はっち退職後は、それまでのネットワークを活かしながら、企画やコーディネート部分に関わり、アートと地域をつなぐ活動を展開している。
金入健雄(かねいりたけお)
青森県八戸出身。第63代公益社団法人八戸青年会議所理事長。今年度は公益社団法人八戸青年会議所理事長として「新しさの港から未来へ~市民の誇りとなる八戸スタンダードの発信~」をスローガンにまちづくり運動を展開中。
最後にアンケートのご回答にご協力お願いします。
https://docs.google.com/forms/d/1IwFexKzawjGKoSbkEKnh-YTkV6aZhPW31Sl2cuxJjPs/edit




